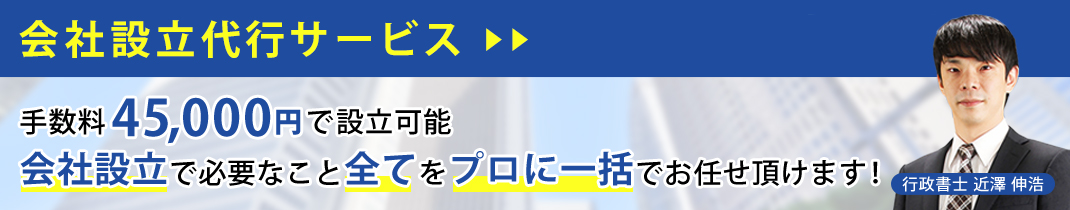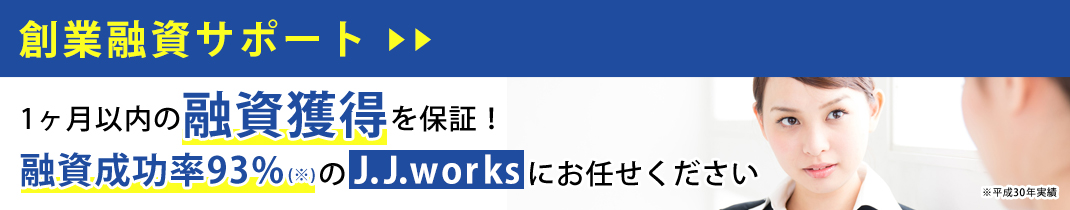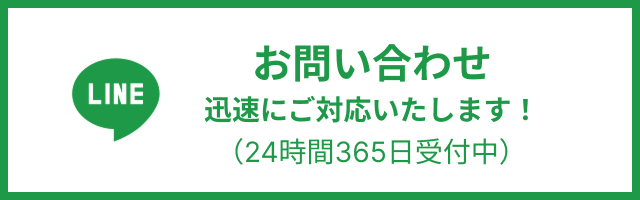会社設立後の役員報酬の決め方と注意する事
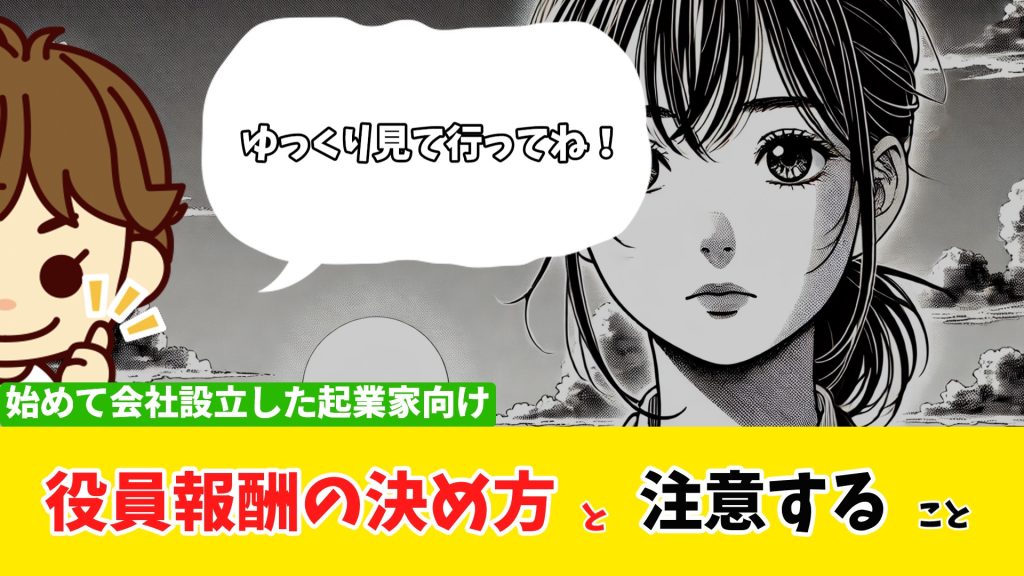
会社の役員が会社から受け取るお金の事を役員報酬と言います。自分で会社設立した場合、自分で役員報酬を決めて支給する事になりますが、従業員の給与と違ったルールがあります。
今回は、会社設立した後の役員報酬の決め方とその際に知っておきたい基本的なルールや手続きの手順などを解説して行きたいと思います。
【このページの目次】
役員報酬とは?
・給料と役員報酬の違い
役員報酬のルール
・役員報酬を決める時期
・その①定期同額給与
・その②事前確定届出給与
・その③業績連動給与
役員報酬を決めた時の手続き
・定期同額給与(株式会社の場合)
・定期同額給与(合同会社の場合)
・事前確定届出給与の場合
役員報酬を決める際の注意点
・社会保険料を考慮しよう
・役員報酬は低い方が社会保険・税金が安い
・経費になる生活費を洗い出そう
・自宅が賃貸の場合は社宅制度を取り入れよう
・会社の利益を考慮して決めよう
・役員報酬を受け取れない月も社会保険と税金は発生する
・会社と個人が負担する税金のバランスを確認する
役員報酬を変更できるレアケース
・役員の地位が変更した場合
・経営状況が悪化した場合
役員報酬金額の例
・最低限の生活費を確保して会社に利益を出す
・勢いで理想の欲しい金額にする
まとめ
役員報酬とは?
給料と役員報酬の違い
役員が会社から受け取る給与の事を役員報酬と言います。ただし、役員報酬は従業員が受け取る給料とは違い、法人税法で細かく厳しいルールがあります。
役員は自分の役員報酬を自由に決められる立場にあるので、一定のルールの元に運用させないと会社が好き勝手して税務署は税金が取れなくなってしまうからです。
詳しいルールは後述しますが、役員報酬は金銭以外にも「会社で何かを支給してもらったり、会社でプライベートな支出をすると」役員報酬とみなされる場合があり、税務署とトラブルになったりします。
その他法人税法上のルール以外にもこんな違いがあります。
| 役員報酬 | 給与 | |
| 勤務実態の有無 | 不要、ニートでも支給OK | 勤務実績に応じて |
| 健康保険・厚生年金 | 勤務時間や金額関係無く加入※ | 勤務時間に応じて |
| 雇用保険・労災保険 | 適用無し | 適用あり |
| 残業代 | 適用無し | 適用あり |
| 最低賃金 | 適用無し | 適用あり |
| 日割計算 | 出来ない | 出来る |
※非常勤役員は加入義務無し
少し分かりにくいのが「勤務実態の有無」ですが、給与は勤務の対価であり、役員報酬は責任の対価となるので、役員報酬は仕事をしていなくても受け取る事が出来ます。
「うちの奥さん全然働かなくて…」という方の場合、役員報酬なら問題なく支給できますが、給与の場合は実態が無い嘘の経費となるというイメージをお持ちください。
ただし、月々30万円程度までの一般的な金額の場合のみです。「不相当に課題である役員報酬」は経費として認めないという例もあるので、不安な場合は税理士さんに相談しましょう。
ここでは給与と違って役員報酬は細かなルールに従わなければいけないんだなという事。その他にも給与とは色々な違いがあるんだなという程度を抑えておいて下さい。
関連リンク
この記事の目次に戻る場合はこちら
このページの目次に戻る
役員報酬のルール
役員報酬を決める時期
役員報酬の金額は、会社設立1年目については毎月受け取る役員報酬は会社設立日から3カ月以内に決定する必要があります。役員賞与(事前確定届出給与)は会社設立日から2カ月以内です。
これらのスケジュールを守らないと役員報酬を損金(会社の経費)にできなくなってしまいます。
損金(会社の経費)に出来ないという事は、役員報酬に所得税や社会保険料といった個人に負担する税金は発生し、さらにその分会社にも税金が発生します。
こうなってしまうと、税金の負担だけで会社が滅茶苦茶になってしまいますので、役員報酬を決める時期はしっかり守るようにして下さい。
毎月受け取る役員報酬の「会社設立日から3カ月以内」に決めるというルールですが、法律では「会計期間開始の日から3月を経過する日にされた定期給与の額」はOKとなっています。
税理士さんによって「これは決算の株主総会を想定しているから…会社設立1年目は会社設立した月から役員報酬を支給しなければダメだ!」という考えの方もいます。
結論から言うとどちらでもいいと思います。会社設立後3カ月以内に決めて税務署に怒られたという例も聞いた事は有りません。考えが違う税理士さんもいると知っておいてください。
その①定期同額給与
決められた役員報酬金額を毎月同額で支給するというものです。こちらは、事業年度開始から3ヶ月以内の株主総会で決定しなければならないと決められています。
世の中で言う3カ月以内に決めるというのは此処から来ています。事業年度から3ヶ月以内の株主総会でという規制をする事で会社に利益調整をさせない仕組みとなっています。
これを事業年度終了直前まで認めてしまうと、利益が出ているから役員報酬増額とされてしまい税務署は税金を取る事ができません。
「事業年度開始から3ヶ月以内の株主総会で決めた金額を毎月同額支給」という事は、1年に1回しか役員報酬を変更する事はできず少しでも金額が違うと会社の経費として認められません。
毎月30万円と決めてしまったら1年間は変更できず、40万円で支給した月は差額の10万円は会社の経費として認められないという事です。
多分皆さんはこの定期同額給与しか使わない方が殆どだと思います。
その②事前確定届出給与
役員報酬は基本的に「定期同額給与」しか会社の経費として認められていません。役員に対する賞与は当然経費として認められません、役員が賞与で会社の利益を調整出来てしまうからです。
しかし、事業年度の最初(事業年度開始後4ヶ月程度まで)に税務署に対して金額や支給日を届出る事で役員に対する賞与も会社の経費として認められます。
事業年度の最初(事業年度開始後4ヶ月程度まで)に税務署に対して支給金額や支給日を届出をさせるので、会社の利益調整が出来ない仕組みになっているからです。
「売上が偏って毎月の役員報酬が出せない…」と困っている会社向けの制度ですが、落とし穴も多いので事前確定届出給与を使いたいという方は必ず税理士さんと相談して決めるようにしましょう。
その③業績連動給与
業績連動給与とは、会社の利益に応じて支払われる役員報酬のことです。定期同額給与や事前確定届出給与はあらかじめ事前に設定した金額を支給しますが、業績連動給与は違います。
業績連動給与は「報酬の算出方法が所定の指標を基礎とした客観的なものである」であり「有価証券報告書に記載・開示している」「通常の同族会社以外である」という3つの条件があります。
つまり、業績に応じて支給してもらえる素晴らしい制度ではありますが「上場企業でしか使えないので我々一般人には縁が無い制度」だと覚えておくといいでしょう。
役員報酬を決めた時の手続き
定期同額給与(株式会社の場合)
定期同額給与の金額を決定した時の手続きですが、株式会社の場合は「株主総会議事録」を作成し、自社で保管するだけで手続き完了となります。
役員報酬額の決定で使うのは定期同額給与と事前確定給与
基本的には定期同額給与を使う
毎月の役員報酬を受け取らないという方はいらっしゃいません。一般的な中小企業は利益連動給与の制度はつかえませんので、殆どの中小企業が定期同額給与の制度を利用しています。
役員報酬は毎月同じ金額でないと会社の経費にならないと覚えてしまうのがいいでしょう。
上級者向け 社会保険料節約で事前確定給与を使う
前述のとおり、事前確定給与とは役員に支給する賞与の事です。あまり利用している会社さんは少ないのですが、社会保険料の節約方法として利用している会社さんもいらっしゃいます。
社会保険料というのは1度の支給が「健康保険料200万円」「厚生年金保険料150万円」までに対して保険料がかかってこないという決まりがあります。
この仕組みを利用して社会保険料を節約するのです。
年収500万円の役員報酬の場合、毎月の役員報酬を年間120万円にして、賞与を380万円にしてしまうのです。こうすれば賞与380万円の一部に社会保険料はかかってきません。
事前確定給与や社会保険の節約については細かい問題点が多いのでご興味がある方は専門家にご相談をオススメします。
役員報酬の変更方法
役員報酬は利益調整が可能という理由から金額の変更に制限があります。毎月の役員報酬金額を変更できるのは以下の場合のみとなります。
1.事業年度終了後3ヶ月以内の株主総会での変更
2.取締役⇒平社員といった立場の変更
3.会社の経営が著しく悪化した場合
役員報酬額の決め方について
一般的な役員報酬の決め方
前述のとおり役員報酬の変更には制限がかかっています。基本的には年1回しか変更する事はできませんので注意して決める必要があります。とはいえなかなかどうすればという方が多いと思いますが
多くの中小企業の社長さんは
α最低限の生活費にして会社に利益を出す
β予想される1年の利益額いっぱいにして会社の節税をする
という2パターンのどちらかで決めるのが主流です。
※こういった方が多いというだけですのであくまでご参考に程度にして下さい。
売上が安定するまでは注意!
売上が安定しない時期、特に会社設立当初は役員報酬が会社から貰えないという事があると思います。こういった時には注意が必要です。
会社にお金が無くて役員報酬を受け取る事が出来ない月、こういった月は役員報酬を受け取った事にしなければいけないのです。なぜなら、毎月同額を支給していないと会社の経費として認められないからです。
結果、役員報酬を受け取った事にしたが為、受け取っていない役員報酬に対する税金や社会保険料を支払う羽目になってしまいます。
売上が安定するまでは、少し会社に利益がでるような金額で役員報酬を設定するのが良いでしょう。